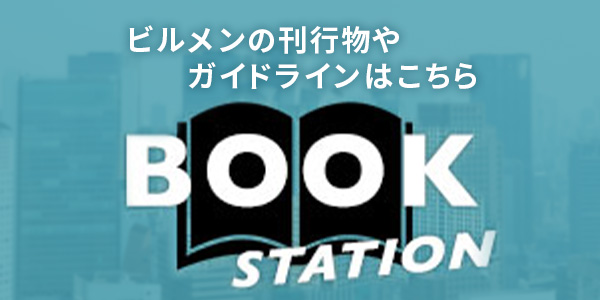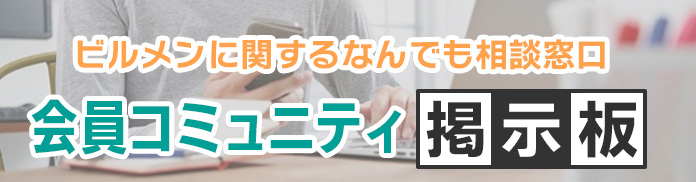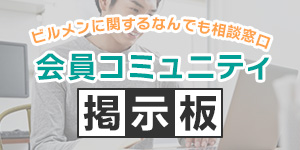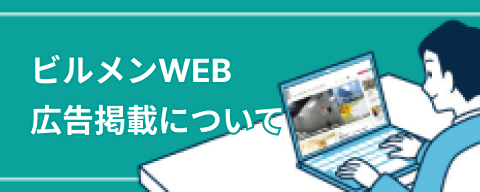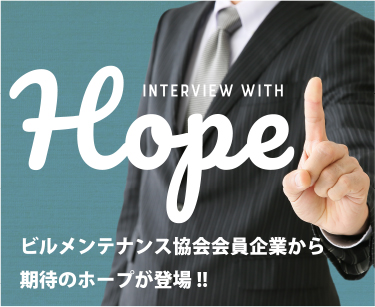
変化を恐れず、使命を果たす
FILE 082
株式会社キタデン・芙蓉株式会社
代表取締役社長 伏木 進

―――株式会社キタデンについて教えてください。
伏木 株式会社キタデンは私の父が創業者になります。当社の歴史は1960年2月に遡ります。父はもともと東京の会社で電気工事業に従事していましたが、北海道支店に赴任し、道内で任されていた工事現場の竣工前に、勤務していた会社が倒産してしまいました。この転機が「北電力設備工事株式会社」を創業し、グループの基盤を作ったきっかけとなりました。
それから電気工事一本でやってきましたが、ビルメンテナンス業に進出したのは昭和40年代です。当時の札幌市は政令指定都市への移行、地下鉄の開業、冬季オリンピック開催など、急速な発展を遂げていました。そんな中、ボイラー業務等を行うビルメンテナンス会社はありましたが、電気設備保守を手掛ける企業はなかなかありませんでした。そこで、電気設備保守管理業務を依頼されるようになり、工事部門は北電力設備工事株式会社にそのまま残し、保守部門を分離する形でビルメンテナンス業へ進出したというのが株式会社キタデンの始まりとなりました。
株式会社キタデンは1973年7月2日に設立され、2023年には50周年を迎えることができました。現在では、電気・空調・給排水設備などを含む設備管理全般を手掛ける他、清掃、施設警備から不動産仲介・管理なども手がける企業となっています。
―――それでは、子どもの頃から会社を継ぐことは決めていらっしゃったのですか?
伏木 いいえ、私は四兄弟の一番末っ子でしたし、継ぐことはないと思っていました。
しかし、小学校の卒業文集で将来なりたい職業に「会社の社長」と書いたことを覚えています。会社の経営者になりたいな、とは子どものころからずっと思っていました。
―――子どもの頃の夢をしっかりと叶えられたのですね。入社されたきっかけや、現在までの経緯はどのようにして社長になられたのですか?
伏木 社長に就任したのは2004年ですが、バブル最盛期の1990年に社会人になり、北海道から離れた東京で都市開発や建築・不動産に関する業種でキャリアを積んでいました。
その後、転職を経て資産管理やM&A等のコンサルティング経験を積み、さらにキャリアアップを目指して中小企業診断士の資格も取得しました。
そんな中、当時の社長である父から「札幌で仕事をしないか」と誘われ、また、妻の「空気の綺麗な環境で子育てをしたい」という希望もあり、東京都心での生活から北海道にUターンする決断をしました。札幌に戻り、電気工事会社の営業職で2年経験を積み、キタデンには専務取締役で入社、1年2カ月で社長に就任しました。東京での不動産やコンサルティングに関する経験は会社経営において非常に役立っています。
―――これまでで一番苦労されたことは何ですか?
伏木 指定管理者制度への移行に伴い、予算の大幅な削減を求められた際、会社としてさまざまな大きな判断を迫られました。その中で設備の現場や従業員の雇用継続を確保するために尽力しましたが、最終的に雇用を守れなかった従業員が出てしまったことが、一番の苦い経験となっています。「従業員を路頭に迷わせるわけにはいかない」という想いから、会社都合で辞めざるを得ない状況を作らないよう、常に「守り」と「攻め」を見極めて経営判断をしていかなくてはならない。また、雇用を守るためにリスクに備え、常に最善の方法を考えることが私の責任であり、役割だと考えています。
―――経営者の立場であると常に判断に迫られることの連続だと思います。判断に迷いがある時や困った時にはどうされていますか?
伏木 真実を見つめ、先入観を捨てることが重要だと考えています。
また、公平性や社会性を意識し、世の中や社会のためになることなのか? お客さまにとって有益か? さらには将来に渡ってどのような影響があるのか? という視点を大切にして判断しています。重要なのは誰かが一人勝ちするのではなく、皆が少しずつバランスよく勝てるようにすることだと思っています。
さらに公平性という観点から、嫌いな人を作らないことが大切だとも感じています。他人を否定せず、視野を広げることが必要だと考えています。
―――これまでで成果をあげられた、うれしかったことなどありましたらおうかがいします。
伏木 色々と挫折もありましたが、その度に乗り越えてこられたところでしょうか。先程お話しした大きな挫折に加えて、札幌市の入札指名停止の時期がありました。その影響で、従業員60名を超える現場が一気に失われ、まさに第二の危機が訪れました。その時、地元の多くの会社に助けていただき、本当に多くの方々に支えられました。その結果、物件が取れず、会社を去っていく従業員もいましたが、その後数年経って戻ってきた従業員もいます。うちの会社では、数年後に戻ってくる従業員が意外といまして。私としては、そういった従業員が戻ってきてくれることが実はとても嬉しいことです。
他の業界に挑戦してみたくて転職したいという気持ちはよくわかります。私もかつて、やりたいことがあって転職した経験がありますから。その中で色々な経験を積んだ結果、「やっぱりもう一度キタデンで働きたい」と扉を叩いて戻ってきてくれる従業員もいます。辞めて戻ってくるというのは勇気がいることだと思いますし、そうした従業員たちの決断に感謝しています。人生には何度でもチャンスがあるべきだと思いますし、そのチャンスを与えることが大切だと考えています。色々な経験を経て成長し、再び活躍してくれる姿を見られるのは、本当にありがたいことです。
また、当社では兄弟や親子で働いている従業員もいて、そういった繋がりを持ちながら一緒に働けることにも感謝しています。勤続年数が長い従業員も多く、30年、40年勤めた従業員へ表彰の機会がありましたが、昨年、勤続50年表彰という方も登場しました! その従業員は職業訓練校で電気を学び、17歳で当社に入社以来、多くの苦労もあったと思いますが、50年にわたり設備技術者として頑張り続けてくれたことを本当に嬉しく思います。
―――これからのビルメンテナンスの仕事にはどのような可能性があると感じていますか?
伏木 この仕事はなくならないと思います。AIやIoT化が進み、機械やシステムに変わる時代が来ることは確かですが、それでも人の手が必要な部分は残るでしょう。とはいえ、この業界はその進展がまだ遅れている部分があると感じています。今後、建物を長く活用していくことは非常に重要であり、ますます求められることは間違いありません。
しかし、同時に運用にかかるランニングコストが増大するのも事実です。ビルオーナーはこのコストを最も気にするので、私たちはその圧縮に応える必要があります。場合によっては、この業界の市場が縮小するといった厳しい可能性に繋がる部分も一部あると思います。このような変化や流れをしっかりと捉え、新しいことに挑戦していかなければ、ビルメンテナンス業は社会に認められないと強く感じています。
―――会社を進化させ成長させるために取り組んでみたいことはありますか?
伏木 当社の強みは、特に「電気設備」の分野において多くの専門家がいることです。この分野において、今でも多くの人材を育成している点が大きな強みだと思っています。
2018年に発生した北海道胆振東部地震(※)では、設備インフラを守ることが社会的な使命だと強く感じました。この時、私たちはその使命に応えるために、多くの人材を育てていかなければならないと実感しました。
地震ではブラックアウトが発生し、非常に厳しい状況が続きましたが、そんな中で私たちの従業員が現場でお客さまの建物を守るために尽力し、非常に感謝していただきました。電気は建物の「心臓」と言える重要な役割を果たしています。災害時には水、空気、電気といったインフラにさまざまな問題が発生しますが、電気が使えないと何も動かすことができません。そのため、災害時に備えた知識や技術を身につけることが非常に重要だと思います。
また、復旧・復電が完了した際には、すべての設備を点検し、安心・安全に問題がないかを確認しています。当社は、お客さまが多く利用される施設の管理も行っており、ビルオーナーに貢献することができました。
私たち一人ひとりが、このような重要な役割を担っているという誇りと社会的な使命感を持って仕事に取り組んでいきたいと考えています。
※北海道胆振東部地震(ほっかいどういぶりとうぶじしん):最大震度7の地震によって最大規模の発電所が損傷し、そこから連鎖的に発電所及び送電の停止、北海道全域が停電するという前例のない大規模停電が発生した。
―――これからどんな会社を目指していきたいですか?
伏木 私はしっかりと北海道で商売を続けていこうと思っています。会社を大きくするために、東京や大阪、名古屋への進出を考える方も多いと思いますが、私は地元である北海道に根を張って活動を続けたいと考えています。現在は札幌市だけでなく、室蘭にも「芙蓉株式会社」というビルメンテナンス業の会社を経営しています。今後も北海道のビルメンテナンス業をしっかりと守り、地域の発展に貢献していきたいと思っています。
私自身、ここで働いている従業員を不幸にしたくありません。だからこそ、私たちは雇用を支える産業であるという意識と、地域のインフラを守る重要性を胸に、この地で続けていきたいと考えています。我々の仕事は一般的に固定の現場で働くことが多いですが、当社では意図的に異動を行っています。例えば、病院での経験を何年間か積んだ後、次は庁舎、その次はホテルと、さまざまな現場を経験してもらっています。これにより、従業員同士の横のつながりが生まれます。この繋がりがあると、例えば「停電作業の応援に行きますよ」とか「配管工事、電気工事を手伝ってください」といった、専門家同士の助け合いができるようになります。
また、年に4回ほど親睦会を開催しています。そこでは昔の現場の仲間とも再会することができます。時には「また異動させたの?」とお客さまに驚かれることもありますが、それ以上に仲間同士が助け合い、協力し合える体制ができることは、非常に良いことだと感じています。


発電状況が表示されたモニターと伏木氏。
Corporate Information
- 株式会社キタデン
- 〒064-0804 札幌市中央区南4条西13丁目1番8号S413ビル
- TEL: 011-512-7222
- 代表取締役 伏木 進 https://www.kitaden73.co.jp/
- 芙蓉株式会社
- 〒050-0065 室蘭市本輪西町1丁目4番2号
- TEL: 0143-50-6555
- 代表取締役社長 伏木 進 https://fuyo60.co.jp/