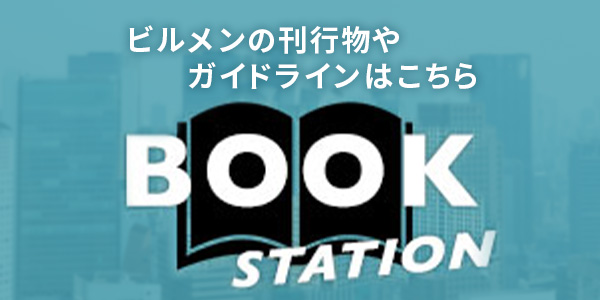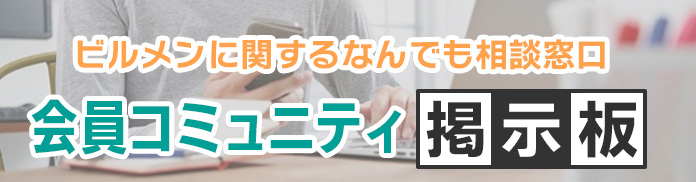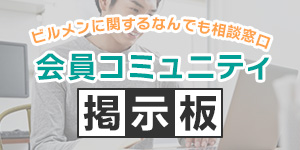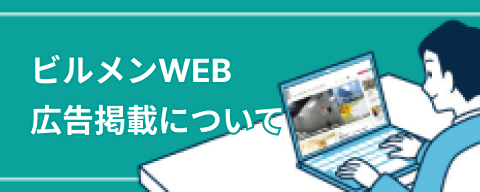価格転嫁7つの心得と15のテクニック講座 第1回
みなさんこんにちは。中小企業診断士の初鹿野浩明(はつかの ひろあき)と申します。このシリーズでは、経営コンサルタントの相談、支援業務といった経験を元に中小企業者は「どうやって価格を上げようか?」という課題に対してのお話をしたいと思います。その中で、価格転嫁の7つの心得と、価格転嫁15のテクニックという内容で全6回のお話を進めます。
今回はその第1回目。物価高の現状についてお話をします。
現在、世は物価高によりインフレとなり、近年の急激な原材料高騰や最低賃金の上昇に伴って、中小企業・小規模事業者の利益は日増しに圧迫されています。特に、ビルメンテンス業のように、労務費の負担が多い事業者であるサービス業などは、価格転嫁が難しい業種と言われています。
1. 世界的な物価高
現在の物価高は、世界的に深刻な問題として注目されています。ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーンの混乱、エネルギー価格の高騰、そしてロシアによるウクライナ侵攻といった要因が重なり、物価上昇に拍車をかけてきました。
日本においても、物価上昇が顕著になってきています。
◇様々な物価上昇
| エネルギー価格の高騰 | 世界的なエネルギー価格の上昇を受け、電気代やガス代が値上がりしています。 | |
| 食料品価格の上昇 | 外食や中食の価格上昇に加え、家庭で消費する食料品価格も上昇傾向にあります。 | |
| サービス価格の上昇 | 外食や旅行など、サービス価格も上昇しており、家計支出に大きな影響を与えています。 | |
| 賃金上昇の遅れ | 物価が上昇する一方で、賃金はなかなか上がらず、実質所得が減少している世帯が増えています。ますます、賃金格差も大きくなっています。 | |
| 日本銀行の対応 | 日本銀行は、緩和的な金融政策を継続していますが、この政策も限界にきています。金利が上がることも時間の問題です。 | |
2.価格転嫁の重要性
日本では、1990 年代のバブル崩壊後、30 年以上に渡り長期デフレ経済が続き、デフレ・スパイラルとも言われていました。その結果、多くの事業者は、値段を下げる経験があっても、値段を上げるという経験がありません。そのため、「価格改定をする」、「値段を上げる」という行為に対して、特に、中小企業・小規模事業者では「不安や恐怖の念」があるのは理解できます。
しかし、ここで、価格転嫁を怠ると会社が立ち行かなくなる可能性が高いです。思い切って「値上げ(価格転嫁)」をすることを決心してください。インフレ局面なら顧客の理解も得やすいのです。

3.価格転嫁のメリット
1)企業の収益性維持
コスト上昇を価格に転嫁することで、企業は収益性を維持し、事業を継続することができます。収益性が低下すると、投資や雇用が減り、経済全体に悪影響が及ぶ可能性があります。
2)賃上げの原資確保
価格転嫁によって得られた収益は、賃上げに充てることができます。インフレ下で賃上げを怠ると、従業員は物価上昇で生活費を圧迫されて実質的な所得低下となり、離脱(離職)せざるを得なくなります。
3)持続可能な生産活動
原材料費やエネルギー価格の上昇に対応するためには、価格転嫁が不可欠です。価格転嫁を行わないと、企業はコスト削減のために品質を低下させたり、生産を縮小したりせざるを得ない状況に陥る可能性があります。
4)サプライチェーン全体の安定化
下請け企業が適切な価格転嫁を行うことで、サプライチェーン(供給連鎖)全体の安定化につながります。下請け企業の収益性が向上すれば、技術革新や品質向上への投資が可能となり、製品の競争力強化に貢献します。
4.労務費の推移
経営者の方々は、最低賃金が急速に上昇傾向にあることは承知していると思います。ここで一度、どの程度の上昇なのかを確認してみたいと思います。 以下は、著者が活動している茨城県の最低賃金の推移をまとめたグラフです。地域ごとに最低賃金の隔たりはありますが、傾向は全国同様であるので参考にしてください。

1995 年~ 2012 年が最低賃金は最も安定しており、この17 年間で、最低賃金の上昇幅は100 円にも達していません。これは、「失われた20 年」ともいわれる時期と一致しています。
また、2016 年以降の伸びが急激になっており、1980 年代のバブル期を上回る勢いで、最低賃金が伸びています。最低賃金が安定していた2001 年(647 円) を100 とすると、2021 年では約1.4 倍(879 円)に、さらに、2024年では約1.6倍(1,005円)と急激に上昇傾向にあります。
本来インフレは、労務費と同じ割合で上昇します。2001年ころの販売単価と比較した時、皆さんの事業の販売単価は、1.6倍になっているのでしょうか?
また、実際の労働者は賃金が上がったという実感を持っていません。インフレとのかねあいの他にも、「働き方改革」による労働時間の短縮なども影響していると考えています。労働時間の短縮や省人化も大切な考え方であると思いますが、限界は捨てきれません。
そのような中で、次回から、今後どのように価格転嫁を図るのか、値上げをするのかという取組を、筆者の経験を交えながらお話を進めていきたいと思います。
◆◇◆
株式会社経営科学研究所 代表取締役
中小企業診断士