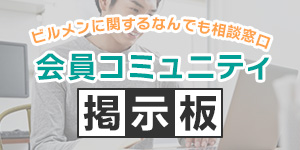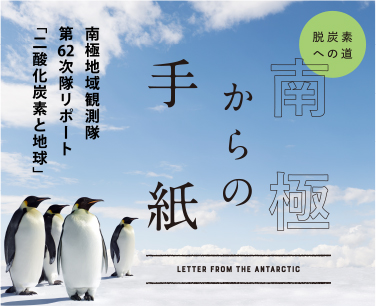
ゴム気球、カイトプレーン、人工衛星……。様々な方法で観測したデータを解析することで、地球の過去と未来が見えてくる。
2021.10.22 17:00 更新![]()
新型コロナウイルスが世界を覆う厳しい状況下、気候変動を始めとする地球の観測を続けるために、日本を出発した第62次南極地域観測隊。脱炭素という二酸化炭素排出削減の加速を求められる現在、南極で得られる環境データは極めて重要だ。その最前線からリポートをお届けする。
24時間体制で行われる昭和基地での気象観測
昭和基地では私が担当する二酸化炭素濃度などの温室効果ガス観測の他に気象観測や地震観測、電離層や地磁気観測など、多くの観測が行われています。これらのほとんどの観測機器は昭和基地に設置されていて、昭和基地における変動を観測しています。しかし、南極観測がカバーする研究エリアは空間的に広く、昭和基地に設置している測定機器では測定できない場所のデータが必要になる場合があります。そのようなときは、観測装置を目的の場所まで持って行って観測しなければなりません。
たとえば、上空の気象状況を観測したいときは「ラジオゾンデ」という観測機器をゴム気球に吊り下げて飛ばします。この装置には地上から上空約30kmまでの気温や湿度、気圧、風向風速の情報を無線で地上に送信する機能があり、昭和基地では毎日2回飛ばして各種データを得ています。普段、このラジオゾンデによる観測をしているのは気象庁から参加している観測隊員によって行われています。他の隊員と違って、24時間休みなく気象観測を実施していますのでとても大変です。一方、気象庁の観測とは別に、荒天時の上空のデータを必要とする研究もあります。そのため、風の強い天気の悪い時にラジオゾンデを飛ばすことがあります。危険を伴うので必ず2名以上で観測を行っています。
南極の気象観測データは一般にも公開されていますので、日本との気温の違いなど比較してみてください。
荒天時の放球の様子
南極の大空を飛ぶカイトプレーン
ラジオゾンデはゴム気球の浮力によって上に飛んでいきますので、垂直方向の観測データを提供してくれます。一方、空気中のエアロゾル(微粒子)を観測する研究では、1000m〜3000mの各高度の面的な分布を観測したいので、その目的の高度に観測機器を留まらせておく必要があります。先のラジオゾンデでは気球の浮力でどんどん上昇してしまいますのでこの方法は使えません。そこで登場するのがカイトプレーンと呼ばれるラジコン飛行機です。翼がカイト(凧)なので固定翼よりも安定性が高く、雪上車にも搭載できる大きさに折りたためるといった利点があります。このカイトプレーンに観測装置を搭載し、目的の高度まで飛行させて観測を行うのです。離着陸はオペレーターが手動で操作しますが、上空では雪上車に設置した基地局からリモートで操縦することができます。
紅色の機体は某アニメに登場する飛行機のようで、真っ青な南極の空に映えるのですが、いかんせん機体が小さいので上空に上がってしまうと双眼鏡で追跡するのも大変です。

組み立てが終わり、最期のチェックを待つカイトプレーン(提供:国立極地研究所)
離陸するカイトプレーン(提供:国立極地研究所)
人工衛星を使った地殻変動の観測
もう一つご紹介したいのがGNSSを利用した南極大陸そのものの動きを捉える観測についてです。GNSS(Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム)は、米国のGPS、日本の準天頂衛星(QZSS)、ロシアのGLONASS、欧州連合のGalileo等の衛星測位システムの総称です。カーナビやスマホの位置情報はこれらのGNSSを使っていますが、精度良くこの位置情報を観測することにより誤差数cmの精度で地殻変動を捉えることができます。この観測には専用のアンテナとデータを記録するロガー、バッテリーを観測点に設置してデータを記録します。この観測は昭和基地のある東オングル島だけではなく、基地から離れた島や大陸の露岩地帯(雪や氷に覆われていない岩盤が露出している場所)で観測をします。ちょうど基地周辺のいくつかの露岩地帯には観測用の小屋があるので、そこに泊まりながら目的地まで雪上車を走らせます。担当の隊員にとって一番心配なのが、「バッテリー切れになってデータが途切れていないか」です。長期間観測できるように、太陽電池が付いている観測装置もありますが、太陽が昇らない極夜期には役にたたず、バッテリーも低温の環境で無事に作動しているか、それとも息絶えているか、観測機を収納しているケースを開けて確認するまでドキドキです。
このようにして得られたデータを解析することにより、現在の南極大陸の地殻変動を捉えるだけでなく、過去の南極氷床融解史や地球内部構造の理解がより進むと期待されています。最近、この分野の研究成果が報告されています。
研究成果「東南極リュツォ・ホルム湾沿岸でのGNSS観測と地殻変動の検出」(国立極地研究所)

GNSSの信号を受信して記録する装置(緑色の部分がアンテナ)をメンテナンスする隊員。(提供:国立極地研究所)
厳しい環境下での観測作業にはトラブルがつきもの
じっと定点で観測するものもあれば、アクティブに目標地点に観測機を飛ばしたり、遠方の観測地点まで出向いたりしながら私たちは日々の観測業務を遂行しています。しかし、激しいブリザードに襲われれば外出禁止になってしまうのでラジオゾンデを上げることができません。日本と違って低温環境では、カイトプレーンのエンジンも凍り付いてしまいます。また静電ノイズや長期の低温でのバッテリーの放電など、南極ならではのトラブルがたくさん発生します。これらトラブルに対処するのも南極観測にはつきものです。しかしどうやったらこのトラブルを解決できるか、時には他部門の隊員のアイデアをもらいながら一つ一つ解決していくプロセスは、南極観測隊の魅力の一つでもあります。

次のフライトに向け意見を出し合う。(提供:国立極地研究所)
様々な場所でエコチューニングを紹介することがあります。その時、初めにお話しすることは、南極大陸の氷床の研究から、地球がかつて経験したことのない温暖化が進行している事実です。
大気中に排出されたCO2は、1年ほどで地球の大気全体に広がります。降雪によって南極の氷床に閉じ込められた大気中の成分を分析することによって、80万年前までの地球大気の状態を知ることができます。
産業革命が始まった250年ほど前から、大気中のCO2濃度は急上昇し、今では400ppmを超えています。少なくとも80万年前から250年前までは、大気中のCO2濃度は200ppm~280ppmの間に抑えられていました。CO2を海洋、大陸、大気間で循環させる地球が46憶年かけて備えてきた自然システムによるものです。これからも南極の伊達さんからのお便りを楽しみにしています。
日本の南極観測について
日本の南極観測のルーツは、今から100年以上前の明治45(1912)年に、白瀬矗(しらせ・のぶ)ひきいる南極探検隊によって実施された学術探検にまで遡る。その後、昭和32(1957)年〜昭和33(1958)年に行われた国際地球観測年(International Geophysical Year; IGY)と呼ばれる純学術的な国際協力事業の一環として、閣議決定に基づき、昭和31(1956)年に第1次南極地域観測隊の派遣が決定し、途中南極観測船の引退に伴う中断をはさみつつ、現在まで60年以上も南極観測を続けている。
第62次南極地域観測隊は、昭和基地での観測、特に長期間にわたり高い品質のデータを取得し、広大な南極大陸に展開された国際観測網の一翼を担ってきた定常観測やモニタリング観測、加えて重点研究観測サブテーマ1「南極大気精密観測から探る全球大気システム」で実施する先端的な観測の継続を計画の中心に据えている。そのため新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、夏期間は、観測継続に必要な人員の交代と物資輸送を最優先として計画し、その他の観測・設営計画は、特に継続性が必要なものに絞りこまれた。
これにより、東京海洋大学練習船「海鷹丸」や南極航空網を用いた別動隊は編成せず、南極観測船「しらせ」を用いた本隊のみによる行動となり、「しらせ」の行動も、我が国の南極地域観測の歴史の中で初めて、他国に寄港しない計画となった。

出典:大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所「南極観測」
日本の南極観測の最前線が昭和基地
1957年1月29日、第1次南極地域観測隊によって東オングル島に開設された昭和基地。開設当初わずか4棟のプレハブ建築からスタートした基地は、今やおよそ70棟に拡大し、自然環境への悪影響を最小限に抑えるため、先進の省エネ技術もいち早く導入されている。発電機の余熱を回収して温水として有効利用するコージェネレーション・システムは、1次隊から採用されている。

第62次南極地域観測隊・越冬隊員
伊達元成(だて・もとしげ)さん
担当:基本観測/モニタリング観測 気水圏変動
所属:国立極地研究所南極観測センター
北海道・伊達市にある「だて歴史文化ミュージアム」で市学芸員を務めていたが、子どものころからの夢であった南極地域観測隊参加の機会を得て、民間から隊員採用された。仙台が生んだ武勇の将・伊達成実公に繋がる亘理伊達家20代当主。