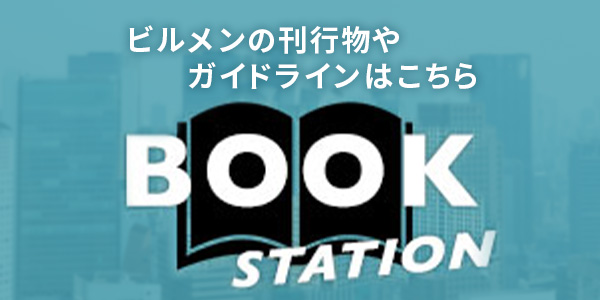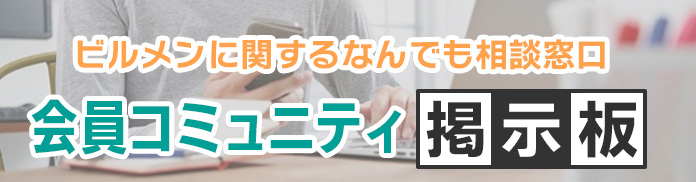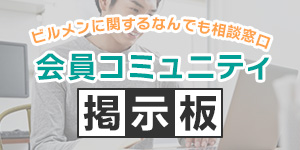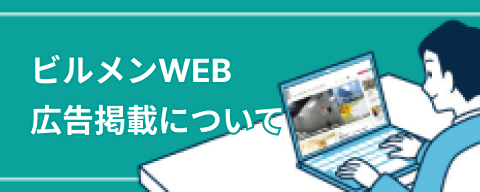【インタビュー】「ビル設備管理技能士」として活躍中!
今回は、設備管理のプロフェッショナルとして、実際に現場で活躍している企業をご紹介させていただきます。
インタビュー
株式会社ボンズビルディングサービスのお二方にお話をお伺いしました。

株式会社ボンズビルディングサービス
代表取締役 家喜 俊也(いえき としや)氏

株式会社ボンズビルディングサービス
設備管理課 主任 井上 史也 氏 (2級ビル設備管理技能士)
<会社概要>
平成30年5月に、アサヒ管財株式会社から「株式会社ボンズビルディングサービス」へと社名変更し設立。総合管理業として、清掃業をはじめ、設備、管理、保全、警備、一部建設業を行い、お客様のどのようなニーズにも対応できる体制を構築。特に設備管理業務は24時間対応で行っており、お客様から評価を得ている。
-- 御社として、どのような事業に注力しているか、また今後の可能性をどう考えておられるか、教えてください。
家喜社長 清掃だけとか設備の点検だけの単体の仕事もありますが、総合管理業として、ひとつの物件に対して、清掃も設備も警備も対応できるよう目指しています。
ただ、どちらかというと設備、保守、保全の方が利益幅が大きいので、そこだけを伸ばしていくということではないですが、設備、保守、保全の方を少し優先的に伸ばしていく可能性はあると思います。
-- 御社では資格手当を支給し、多くの社員にさまざまな資格を取得させることにより、社員にとっても会社にとってもプラスアルファになっているとのことですが、本資格を取得した社員がいることのメリットを感じていますか?
家喜社長 資格を取ることは社員自身の武器になると考えているので、どの部署にも勧めています。特に設備管理に関してはさまざまな資格があるので、どんどん勧めています。多くの社員が資格を持っているということは会社にとってプラスになるので、資格手当として還元しています。
得意先さまや新たなクライアントさまからの見積依頼に対して、社員が資格保持することによって見積の企画力が上がるため、受託率の向上に繋がっています。

-- 井上主任は普段どのようなお仕事をされていますか?
井上主任 常駐ではなく、さまざまな物件を巡回しています。その中でいろいろな種類の設備を点検しています。また、何かあったときにオーナーさまからの要望に応えています。
-- 具体的にどんな要望がオーナーからあり、どのように応えたのか教えていただけますか? また要望に応えたときの反応もお聞かせください。
井上主任 何か問題があった時に自身で原因の特定・解消ができればパフォーマンス向上に繋がると考えています。オーナーさまからすれば一般のお客さまやテナントさまが先にいる以上、要望に対して解決する速度感も重要ではないかと考えています。
実例として、テナントさまからの要望でオーナーさまより共用部炊事場水栓の不具合調査依頼を請けた際、当日中に改修し使用可能な状態で完了できた時は、テナントさまにもオーナーさまにも迅速な対応に感謝いただきました。また皆さまが利用されるトイレの水洗の故障・排泄設備の故障を長期間放置すればクレームに繋がりかねません。
大きい故障であれば調査・改修に業者手配となるのも仕方ありませんが、自身で特定・解決できれば対応時間もコストも削減でき、喜んでいただけるのではないでしょうか。

-- 2級ビル設備管理技能士を取得したことにより、自身の武器や会社としての強みに繋がったと思いますか?
井上主任 資格自体が武器になるというよりも、資格取得のための勉強等の経験が武器であるという実感はあります。現場での仕事のために持っておくと良い知識、と考えると武器になっていると思います。
簡単な実例ですと、とある施設の排泄設備の漏水や排水されない等の故障に際し、現地にいる社員と電話のやり取りで不具合箇所を特定したり、そのまま不具合の解消に繋がったこともありました。知識がなければ自らが現地に行って確認し、原因特定のための試行を繰り返し、最悪の場合、特定に至らず業者への調査依頼になることを考えると、大幅な手間と経費が削減できました。
もちろん現地確認や試行は大事ではありますが、資格取得が業務パフォーマンス向上のための武器になったと言っていい事例だと思います。同様にお客さまのご要望に確実かつ迅速に応えることが会社としての強みに繋がったと思います。

-- ビル設備は年々高度化しており、その管理業務も大きく変化していると承知しています。そうした変化にあった資格はどうあるべきか、お考えをお聞かせください。
井上主任 複数設備の統合や技術の発展により簡素化・自動化され、使用は使いやすく便利になっている反面、設備自体は複雑化し、メンテナンスや改修も専門業者頼みになってきていると感じます。そういうところでは、資格を取得しているだけでは問題解決に繋がらないと思います。
今後もっと専門設備が増えることを想定し、その専門設備を扱えるような専門の資格取得のための一助にもなる資格になればよいのではないでしょうか。具体的に言えば、ビル設備管理技能士資格保有者は他の資格取得のための実技の一部、もしくは学科の一部を免除されるなど、設備管理を目指すにあたり入口のような資格であれば、取得した身としてたいへん嬉しく感じます。
-- ビル設備管理技能士の取得を目指して勉強した際のご苦労話、熱意、受検の際の感想や合格したときの思いなど、その技術・知識がいまどのように活かされているのかをお聞きかせいただけますか。
井上主任 実技に関しては現場での経験を踏まえて一定の知識は有しているつもりでしたが、学科合格に苦労しました。
自身のスキルアップもありますが、資格取得費用を会社から支給していいただいていたので緊張感がありました。合格後は社長より労いの言葉をいただき、喜びよりも安堵の方が強かったです。
技術・知識は前述のとおり業務の効率化、ひいてはお客さまからの肯定的な評価という形で活かされていると考えています。
-- 設備を維持・管理し、突発的な事故にも対応できるような知識を持っておくべきだと思いますが、その知識とは具体的にどのようなものとお考えですか?
井上主任 例として水栓の漏水の場合、水栓の開閉状況と漏水箇所等により該当パッキンを特定できます。これは実際ビル設備管理技能検定で履修した部分です。どの設備も丁寧に使用していても劣化は防げませんし、中には天井裏で逆勾配に敷設されている排水管等設置段階で不具合のある建築物もあります。
そのような状況で適切な改修提案を早い段階で出せることは重要なことであると考えます。
-- 設備機器に不具合が生じた際にはメーカーに任せる部分もあるため、お客さまとの間に入り、問題が起きないように日々点検することがビル設備管理技能士の大切な使命だと思いますが、具体的な事例をお聞かせいただけますでしょうか?
井上主任 メーカー側は丁寧に詳細に説明していただくのですが、例えば「制御盤内サーマルリレーがトリップしているので、調査後不具合箇所を交換」と言われて、理解されるお客さまはそう多くないかと思います。
オーナーさまは「業務に影響が出る」という理由で調査に否定的だったのですが、事故防止のための部品が作動していることを丁寧に説明してご理解いただき、問題なく改修できたことがありました。設備機器の知識だけではなく、オーナーさまの立場に立って、ビルの安全を確保する、無駄なコストを抑えるなどの視点を持ち、円滑に管理を進めるための交渉能力も必要だと思います。

-- 会社として「ビル設備管理技能士」をどのようにとらえていますか?
家喜社長 時代とともに少し内容等を変えていってほしいと思います。特に設備については年々変化していっているので、時代に合った資格に改善をしていっていただけたらと思います。
また、ビル設備管理技能士の受検資格は、実務経験が2級は2年、1級は7年必要ですが、1級は7年も必要だとなかなか資格を取りに行かない人が多いと思います。もう少し実務経験が短くなれば受検者も増えるのではないでしょうか。
-- ありがとうございました。
ビル設備管理技能士のページへ
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/equipment-technician
※2025年度のスケジュールは4月下旬公開予定です。