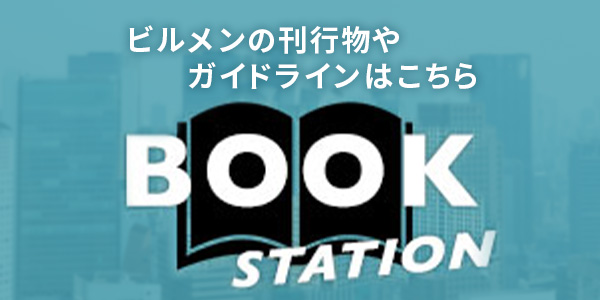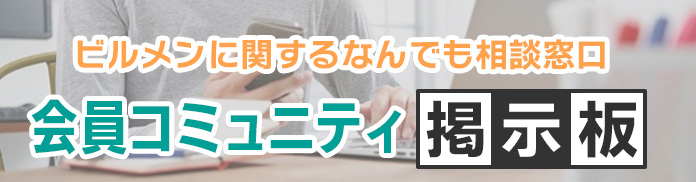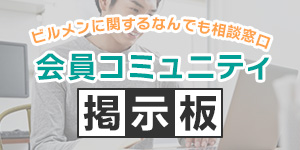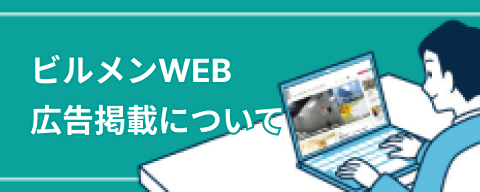いまさら聞けないChatGPT(生成AI)講座 第2回
前回はChatGPTの基本的な使い方を紹介しました。
ChatGPTからの回答内容が箇条書きになっていたり見出しがついていたりと読みやすく配慮され、今までのWeb検索(キーワード検索)とはまったく様子が変わっていることを実感されたと思います。
今回はさらに一歩進んだ「ビジュアル機能」と「ビジネス活用での注意点」について解説します。生成AIをより実践的に活用するために、ポイントを押さえておきましょう。
1. ビジュアル面で活用できる機能
1-1.絵文字の活用
ChatGPTは絵文字を使った表現にも対応しています。コミュニケーションを円滑にし、メッセージをより親しみやすくする効果があります。スマホで文字入力する際など、絵文字を探す手間が省けます。(図1)

1-2.表の作成
ChatGPTは箇条書きの文章などを表にまとめる機能が優れています。「表にまとめてください」というプロンプト(入力)が重宝します。(図2)

1-3.画像生成
言葉で説明しただけでAIが画像を生成する技術も進化しています。ChatGPTと連携した画像生成ツールを使えば、「桜の花見で盛り上がる河原」などのシンプルな指示で、オリジナルのイラストや写真を瞬時に作り出せます。(図3)

SNS投稿やプレゼン資料、ブログ記事のビジュアルを効率的に作成できるため、創造性が広がります(商業利用可)。
1-4.グラフ作成
データ分析やレポート作成時に役立つのがグラフ生成機能です。数値データを提示してChatGPTに指示を出すと、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなどを自動的に作成してくれます。(図4)
複雑なエクセル作業を軽減したり、視覚的に説得力のあるプレゼンテーションづくりが可能です。

1-5.動画生成(Sora)
最先端の生成AI「Sora」は、文字から動画を作成することができます。(図5)
プロモーション動画や教育コンテンツ、ショートムービーなど、用途は無限大です。今後ますます活用の幅が広がり、マーケティング分野を中心に多くの企業が注目しています。

2.ビジネス活用での注意点
基本的なテキストでの応答とビジュアル面を抑えたら、いよいよビジネスで活用するための準備に取り掛かりましょう。そのためにはいくつかの注意点を抑えておく必要があります。
2-1.著作権
AIが生成したコンテンツに関する著作権は複雑です。特に、AIが学習した元データに著作権が存在する場合、生成物が権利を侵害する可能性があります。企業で利用する際は、生成コンテンツの使用範囲を明確にし、事前に弁護士など専門家への相談が必要です。
ちなみに、ChatGPTで生成した画像を自分で商業利用することは基本的に可能です。他の生成AIサービスについては各サービスのガイドラインに従ってください。
AIによる著作権についてのガイドラインは文化庁のサイトが参考になりますので確認してください。(図6) チェックリストや弁護士による動画解説など細部にわたりカバーされています。

2-2.情報漏洩・プライバシー
ChatGPTを使う際、機密情報や個人情報を安易に入力すると情報漏洩リスクがあります。特にクラウド型サービスは、入力したデータがサービス提供者のサーバーに一時的に保存されることがあるため、機密性の高い情報を入力しない運用ルールを徹底しましょう。
ChatGPTでは、入力した情報が学習されない(オプトアウト)設定ができます。(図7)

2-3.コンプライアンス・社内体制
業界ごとに異なる規制やコンプライアンス基準が存在します。生成された情報が法律や倫理的な基準を満たしているか確認が求められます。AIが生成した内容を最終的に人間がチェックするプロセスを整備し、企業全体でのガイドラインを設定することが重要です。
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)による「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」を参考にしてください。無料のPDF資料が配布されています。(図8)

東京都で無料一般公開されている「文章生成AI利活用ガイドライン」のPDF資料も参考になります。(図9)

2-4.ハルシネーション(誤情報)
ChatGPTの大きな課題の一つが、存在しない情報をリアルに生成する「ハルシネーション」です。これは誤った意思決定や誤情報拡散の原因となり得るため、特に顧客対応や外部向け文書で使用する際は注意が必要です。生成された情報は必ず複数の情報源で確認し、信頼性を確保しましょう。
生成AIによるハルシネーションの例(図10)。
| 事例 | 説明 |
|---|---|
| 架空の映画のあらすじを生成する | 存在しない映画のタイトルをAIに尋ねると、実在しないにもかかわらず、もっともらしいあらすじやキャスト情報を生成することがあります。 |
| 数値計算の誤り | AIが複雑な数値計算を行う際、正確な結果を出せず、誤った数値を提示することがあります。 |
| 歴史上の人物に関する誤情報 | 歴史上の人物についてAIに質問すると、生年や出身地などの基本的な情報を誤って提供することがあります。 |
| 存在しない裁判例の引用 | 弁護士がAIを利用して法的調査を行った際、AIが実在しない裁判例を生成し、それを本物として引用してしまったケースがあります。 |
| 架空の理論や用語の創出 | 科学的な質問に対して、AIが現実に存在しない理論や用語を作り出し、あたかもそれが実在するかのように説明することがあります。 |
▲図10:ハルシネーション例
ChatGPTはビジュアル活用をはじめ、さまざまな分野で非常に有用なツールですが、その利便性の裏には注意点もあります。これらを理解し、適切な運用ルールを設けることで、生成AIの恩恵を最大限に引き出しましょう。
※付記. ChatGPTのスマートフォンアプリ
ChatGPTの公式スマホ専用アプリがあります。ChatGPTに類似するアプリが氾濫していますので、開発者が「OpenAI」であることを確認してください。(図11)

それでは、次回からは具体的なChatGPTのビジネス活用法をたっぷりご紹介していきますのでお楽しみに。
※この記事の文章にはChatGPTなどで生成した内容が含まれています。
◆◇◆
杉山 貴思(すぎやま たかし)

【現職】G-word(グッドワード)代表
【肩書】次世代人工知能学会副会長/ソブリンAIプロデューサー/ビジネスコンサルタント
ChatGPT 等の生成AIを中心にテーマとして全国で登壇活動をこなす。衆議院会館や国連大学、早稲田大学、学習院大学、山形大学等で登壇し、生成AIのデモンストレーションが参加者から好評。国内初の(一社)日本情報技術協会認定AIプロデューサーで企業・組織のイノベーションを指導する実力者。複数の大学教授らとのAI研究に参加。ECコンサルタントとしても多数の実績がある。小冊子やハンドブック、雑誌コラムなど執筆もこなす。YouTubeに最新のビジネス情報を公開し、大学関係者や企業家等から好評を得ている。
【Webサイト】
https://www.g-word.jp/
https://ameblo.jp/g-word