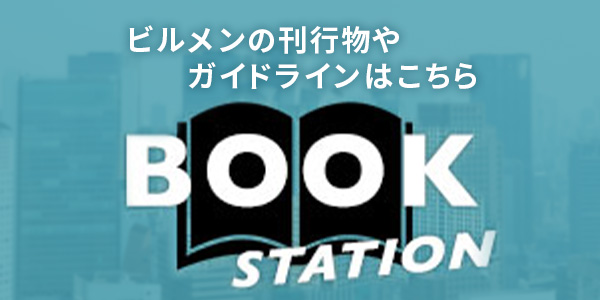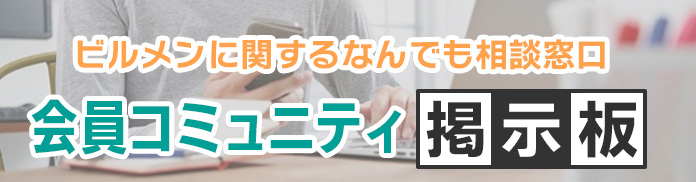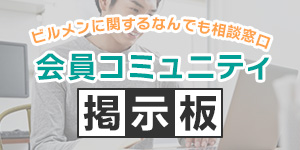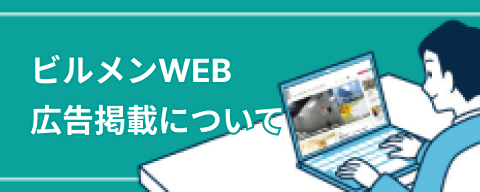【ビル設備管理作業員の皆様必見!】ビルオーナーが求めるビル設備管理技能士とは
ビル設備機器の高度化に伴い、設備管理業務のユーザーベネフィットや実務は大きく変化しており、ビル設備管理技能士に求められる役割も大きく変化してきております。
ビル設備管理技能検定がスタートしてから今年で30年目を迎えますが、ビルメンテナンス業界におけるビル設備管理技能士の今後の在り方をどのようにすれば良いかをテーマに議論を交わしました。
<ご参加者>
小原 康弘 氏 西日本ビル管理株式会社 代表取締役(全国ビルメンテナンス協会 資格試験委員会副委員長)
家喜 俊也 氏 株式会社ボンズビルディングサービス 代表取締役
坂口 勝雪 氏 太平ビルサービス株式会社 技術部 技術部長
清宮 仁 氏 昌平不動産総合研究所 取締役(全国ビルメンテナンス協会 保全委員会委員)
小原 本日はご多忙の中、「ビル設備管理技能士の今後の在り方」をテーマにした座談会にご出席いただき、ありがとうございます。
ビルクリーニング技能検定とビル設備管理技能検定は、どちらも厚生労働省から試験機関として指定を受けた全国協会の根幹をなす事業であり、国家検定の一翼を担うという責任を念頭に置いて取り組んでいます。
しかし、ビル設備管理技能検定はビルクリーニング技能検定と比べ、年々の受検者数の減少が顕著です。1996年の同検定スタートから約30年を経て、技能士の価値をさらに高めるため、これまで築き上げてきたビル設備管理技能検定を礎に、全国協会は同検定の見直しに着手しました。 見直しにあたっては、さまざまな立場の方からそれぞれのご意見があると考えており、それをお聞かせいただきたく、本日の座談会を企画しました。ビルメンテナンス事業者、ビルオーナー、それぞれのお立場から、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

司会 坂口さんは全国協会が指定試験機関として実施しているビル設備管理技能検定において、試験問題を作成する委員としてお願いしています。一方、お勤めの企業では人材育成を含めた技術教育の全般を担っていると伺っていますが、現在のビル設備管理技能士の持つべき技能、知識についてどのようにお考えでしょうか。
坂口 ビル設備管理業務に関係する資格として、まず浮かぶのがボイラー技士や冷凍機械責任者、電気主任技術者といった資格です。それぞれの設備機器を運転・管理するのに必要な資格だからです。それに対してビル設備管理技能士は「ビル設備管理という業務に携わる」知識を評価する資格と考えています。技能検定に合格して技能士の称号を得ることで、ビル設備管理に対する個人的な能力を証明する資格と考えています。
そのような点から、弊社では自社内の人事評価制度の一つとして1級ビル設備管理技能士を含めた資格取得を奨励しており、一部は資格取得を昇進制度に採り入れています。
司会 家喜さんはいかがでしょうか。
家喜 弊社は地元の兵庫ビルメンテナンス協会に入会し、兵庫協会と全国協会からいろいろな情報をいただいており、こういった資格がありますとか、今、資格を取得するための受付期間であることなどを認識しています。いただく情報を選別し、各部署の長が部下の勤続年数や業務の繁忙有無を確認しながら資格取得を勧めています。
坂口さんがおっしゃるとおり、ビル設備管理技能士は「この資格がないと仕事ができない」ものではなく、むしろビル設備管理における全般的な知識があることを担保する資格だと考えています。 弊社ではこの資格が国家検定であることに価値を見出し、ビル総合管理を行う上で必要な資格の中の一つとして捉え、社員に対して積極的に取得を勧めています。
司会 ビル設備管理技能検定を見直すにあたり、まず「今後のビル設備管理技能士はどうあるべきか?」が根幹になると思います。ビル設備管理技能士が今後、どのような方向に進んでいくと良いとお考えになりますか?

坂口 この資格が明確に業務と結びつくことが重要だと思います。目指すのは、ビル設備管理業務においてこの資格を必要とする物件が増えてくることだと考えます。「この資格を持っている人がいるから、この仕事を任せられる」といった要件を備えれば、資格取得を目指す方が増えるのではないでしょうか
家喜 私も坂口さんの意見に賛成です。資格の目指すべき方向性を決めることは大事です。
ひとつの考え方ですが、今後、全国協会が「ビル設備管理技能士」の1級と2級の位置づけをより明確にし、1級の技能士ができること、2級の技能士ができることを明確にできれば、より、技能士を取得しようとする方が増えるのではないかと考えます。
司会 それでは、ビルオーナーから見たビル設備管理技能士のあるべき姿について、清宮さんよりお話をお聞かせいただけますか。

清宮 坂口さんからお話しがありましたように、ボイラー技士、冷凍機械責任者、電気主任技術者など、それぞれの設備機器の専門資格があるので、ビルオーナーの立場から考えれば、ビル設備管理技能士に設備機器の高度な知識や技術を求める必要はありません。法で規制されているような機器の運転管理は、専門資格技術者に頼むからです。
しかし、専門の資格者はそれぞれの設備機器「個」に対しては高度な知識や技術を持ちますが、ビル「全体」の設備機器を俯瞰して、適切に運用・管理することは学んでいないと思います。ビル設備管理技能士はそこをサポートしてくれる存在として期待しています。具体的に言えば、オーナーやテナントがエアコンを操作してもうまく動かないとか、故障が疑われるときなどに助けてもらえる存在だと思います。
ですからビル設備管理技能士は、設備機器の構造より「ビル全体の運用マネジメントや故障時のオペレーション」などに特化するのが良いと思います。皆さんの会社にも、中小ビルならこんなトラブルがあるなどノウハウが蓄積されているはずです。そうしたトラブルへの適切な対応、ひいてはトラブルを起こさないために普段から適切な設備の運用マネジメントができる方であれば、オーナーにとって価値のある資格になると思います。
司会 ビル設備管理業はサービス業と位置付けられていますので、ビルオーナーの期待に応える、言い換えれば「顧客に買ってもらえる価値がある」資格者にするというご意見に感銘を受けました。それが坂口さんからのご意見にもあった「この資格を持っているから、この仕事を任せられる」につながると思います。
さて、清宮さんは全国協会の保全委員会の委員としてもビル設備管理技能検定の見直しに取り組んでおられますが、その内容を少しご紹介いただけますか?
清宮 保全委員会では、2つの軸で見直しを考えています。一つは先ほどお話しした「顧客であるビルオーナーから求められる資格にする」こと、もう一つは「法的な位置づけを強化して技能士の社会的な地位を高める」ことです。この2つをもって、技能士を増やしていきたいと考えています。
後者については、国土交通省が各府省庁の施設管理者が建築保全業務の参考として5年おきに改訂している「建築保全業務共通仕様書」と「建築保全業務積算基準・要領」に、ビル設備管理技能士を明記してもらう活動を進めています。
建築保全業務積算要領には「技術者区分」として、それぞれのレベルの技術者の定義が示されています。実は「清掃」と「警備」には、ビルクリーニング技能士、施設警備など資格が明記されていますが、ビル設備管理技能士はありません。ここに明記されれば、少なくとも公共施設に見積りを出す際に適用することができるので、ビル設備管理技能士の価値が高まるはずです。
もう一つ、国土交通省ではこの技術者区分ごとに毎年2月「建築保全業務労務単価」を公表しているので、そういった点でも技能士の価値が高まると思っています。
司会 保全委員会では「建築保全業務労務単価」を適正な単価にするための活動もされていますね。
清宮 この単価は、国土交通省が毎年実施する「建築保全業務労務費等調査」をベースに算出されています。ですから単価を実勢にあった適正なものにするためには、事業者の皆さんからきちんとデータを出してもらうことが欠かせません。ビル設備管理技能士は3,500名以上おられるので、その価値を社会的に認めていただくために、調査への回答を啓発する活動を行っています。
司会 清宮さんのお話を伺って、家喜さんはどのようにお考えになりますか?

家喜 この資格の価値と認知度を高めるために、全国協会がいろいろな取り組みを行っていることがよくわかりました。 技術者区分に明記するというアプローチは、国の施設や地方自治体の施設などの入札に参加している企業は価値を見出せると思いますが、民間の施設を中心に受注している会員については、どのように考えておられますか?
清宮 官公庁と民間では発注の形態が違うことは承知しています。しかしながらビル設備管理技能士の価値を高めることに、官公庁と民間に違いはないと考えています。例えて言えば国のお墨付きをいただき、今まで以上に認知度を高めることができれば、それを契機として民間のビルオーナー向けにもキャンペーンなどを展開し、啓発活動を強めることができると思います。
まずは、官公庁で実績をあげるというアクセルを踏んで、それを民間にも波及することを目指したいと思っています。
坂口 清宮さんの仮説に同意することは多分にあり、すごくよくわかります。そうなると検定試験で確認すべき内容や試験範囲の考え方は、大きく見直す必要がありますね。それも相当に困難を伴うものと思います。
清宮 かなり難しいテーマであることは承知しています。そのため私が所属する保全委員会では、今日の座談会のテーマでもある「本来のビル設備管理技能士のあるべき姿」について、ゼロベースで見直すこととして議論しています。
司会 試験の話が出てきましたので、そちらのテーマに移りたいと思います。
皆さんの議論をお聞きし、「今後のビル設備管理技能士はどうあるべきか?」の方向性が見えてきたと思います。そうすると、次のステップは「あるべき技能士が持っていなければならない技能」を定義し、その「技能を評価する試験」へと変えていくことになると思いますが、これについて皆さんはどうお考えでしょうか。
小原 地方だと、昔は常駐設備員がいた規模のビルでも巡回で対応しています。会社としては、オーナーさんから緊急対応能力を求められているのかなと思っています。
良いビル設備管理技能士は、コミュニケーション能力が高い人で、オーナーやテナントさんが求めるものを的確に把握して、意見を求められたら提案ができるという能力が求められているように思います。
家喜 技能検定試験を再構築する際には、「1級」と「2級」の定義づけも整理する必要があると思います。
清宮 確かに現状では、1級と2級は試験内容が重複している部分もあり、明確な差が分かりにくくなっています。見直しにあたっての私の提案は、2級は中小ビル、1級は大規模ビルに対応できるというものです。
建物は規模によって設備面で大きな違いがあります。空調を例にとっても、大規模ビルでは地域冷暖房や吸収式冷凍機などを扱わなければならないこともありますが、中小規模のビルではほとんどがビル用マルチエアコンやパッケージエアコンです。まずは中小規模ビルにターゲットを絞った2級を考え、それ以上の大規模ビルを運用する際に必要となる知識・技術を1級にすれば、明確な違いが出てくると考えています。
家喜 経営者の立場では、まず「その資格を取って何がプラスになるのか?」を考えます。ビル設備管理技能検定は東京と大阪でしか受検できないし、数万円もの出張費を出してでも取得させるメリットがあるかと考えると、他の資格を受けさせることも考えてしまうところです。
清宮 保全委員会でも、受検のしづらさは課題として認識しています。東京と大阪だけでなく、全国で受検できるのが理想です。先ほどご提案したとおり、ビル設備管理技能士に必要な技能が「設備機器の運用マネジメント」であるならば、実技試験もこれまでのように実際の機器を分解・整備するのではなく、顧客が望む設備機器の運転監視や点検を行うにはどうするか、トラブルが発生したときの一時対応はどうするかといった内容にできるので、コンピュータ上での試験も可能になると考えています。
一足飛びにデジタル化ができないとしても、全国にある職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)の施設を利用して実技試験を行うというアイデアもあります。技能検定もポリテクセンターも所管は厚生労働省ですので、交渉の可能性はあるものと思っています。
家喜 確かに全国のポリテクセンターと連携して試験を実施できれば、47都道府県すべてで受検することができますので、検討する価値がありますね。
坂口 先に申し上げたとおり、技能士が何らかの登録の要件とか、あるいは入札の要件になるというのが一番インパクトがあります。そこに至ることを踏まえた技能検定の見直しだと思いますので、技能士の価値が高まり、受けやすい試験になり、受検者が増え、合格者が増えるという循環ができると素晴らしいと思います。

司会 最後に本日の締めくくりとして、皆さんのご意見に対する感想と、今後、全国協会として検討すべき課題について、小原さんよりお願いします。

小原 皆さんが虚心坦懐に話されているのをお聞きして、まずはビル設備管理の仕事の奥深さを再認識することができました。そのうえで、資格を所持された方が本当にその職位にふさわしく、ビル設備管理技能士として誇れるような資格にしていく姿が見出せたように思います。設備機器の専門的な知識だけでなく、特にビルオーナーのさまざまな困りごとに的確に対処できる技能を備えることが重要なのだと認識しました。
これまで全国協会の保全委員会が主体的にビル設備管理技能士の見直しを検討してきましたが、これからは私も所属している資格試験委員会との合同プロジェクトチームで、より具体的な「真に社会から求められる技能士」の誕生に向けた仕組みづくりを行っていくこととしています。
ビル設備管理技能士が顧客や社会から求められ、受検された方や企業が「取得してよかった」と思っていただける資格に昇華させていきたいと思っていますので、一人でも多くの方に受検していただきたいと思います。本日はありがとうございました。